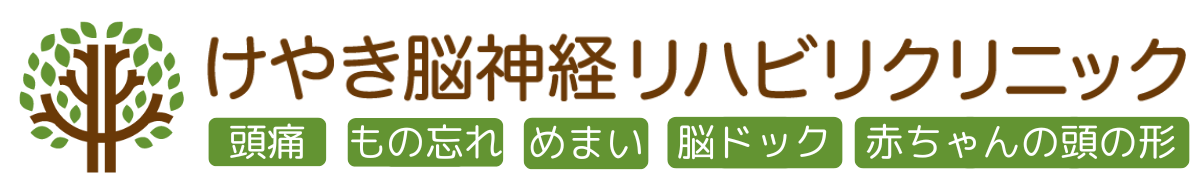脳梗塞予防の鍵「頸動脈エコー」とは?【MRIとの違い・費用も解説】見えないリスクを可視化

脳梗塞は日本人の死因上位を占め、突然発症することが多いため、予防が極めて重要です。しかし、一般的な健康診断だけでは、その隠れたリスクを見つけるのは困難です。
あなたがもし「脳の健康に不安を感じている」「高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある」「ご家族に脳梗塞の既往がある」といった場合、ぜひ知っていただきたいのが「頸動脈エコー検査」です。
この検査は、脳への血液供給の「玄関」とも言える頸動脈の動脈硬化の進行度や、脳梗塞の引き金となるプラーク(血管内のコレステロールの塊)の有無、その危険性を痛みなく、安全に評価できます。
当記事では、「頸動脈エコーの重要性」「MRI(MRA)との連携による精密診断のメリット」「検査が推奨されるケース」「当院の検査体制」「費用と保険適用」について、解説します。
首の血管「頸動脈」の重要性と動脈硬化のリスク
頸動脈は、心臓から脳に新鮮な血液を運ぶ、首の左右を走る非常に重要な太い血管です。まさに「脳の入り口の血管」とも言えるこの血管が健康であることは、脳が正常に機能するために不可欠です。
しかし、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)や喫煙などにより、この頸動脈の壁が厚くなったり、プラーク(コレステロールなどの塊)が付着して血管が狭くなったり詰まったりすることがあります。これが動脈硬化と呼ばれる状態で、脳の血流が悪くなり、最終的に脳梗塞のリスクを大幅に高めることになります。
頸動脈エコー検査でわかること:見えない脳梗塞リスクを可視化
頸動脈エコー検査は、超音波(エコー)を使って頸動脈の内部をリアルタイムで観察する、非常に負担の少ない検査です。
頸動脈エコーの検査方法と特徴
- 非侵襲的:
- ベッドに横になり、首にゼリーを塗ったプローブを当てるだけ。痛みは一切ありません。
- 安全
- 放射線を使用しないため、被ばくの心配がありません。妊娠中の方でも安心して受けられます。
- 短時間:
- 所要時間は約10〜15分と、忙しい方でも気軽に受けられます。
- 準備不要:
- 基本的に食事制限や特別な準備は必要ありません。普段通りの服装でお越しいただけます。
頸動脈エコーでわかる「脳梗塞のサイン」
この検査で、脳梗塞の「見えないリスク」を可視化できます。
- 血管の壁の厚さ(IMT)
- 動脈硬化の初期段階で血管の壁が厚くなる変化を数値で評価します。
- プラークの有無と大きさ
- 血管内にコレステロールなどの塊(プラーク)があるか、その大きさや数を確認します。
- プラークの性状
- プラークが「硬い」のか「柔らかい(不安定)」のか、すでに飛んだ(剥がれた)形跡のある潰瘍性プラークなのかといった、最も危険度の高い情報を詳細に評価します。不安定なプラークは、血管壁から剥がれると血栓を飛ばし、突然の脳梗塞を引き起こす危険性があります。
- 血流の速さ・乱れ(狭窄の有無)
- 血管の狭窄(狭くなっている部分)の有無やその程度、血流の乱れを確認し、脳への血液供給が十分か評価します。
頸動脈エコーとMRI(MRA)の違いと併用メリット
当院では、頸動脈エコーと並行して、必要に応じて頸部MRI(MRA)も併用して行っています。それぞれの検査には異なる得意分野があり、組み合わせることで、脳梗塞のリスクをより「立体的な視点」で評価することが可能になります。
各検査の比較:頸動脈エコー vs MRI(MRA)
| 比較項目 | 頸動脈エコー | MRI(MRA) |
|---|---|---|
| 検査方法 | 超音波 | 磁気画像 |
| 見える情報 | 血流の動き、プラークの性状、血管壁の厚さ | 血管全体の形、狭窄の程度、脳内の血管まで確認可 |
| リアルタイム性 | ◎(今、まさに何が起こっているかを見ます) | △(静止画で血管の全体像を見ます) |
| 放射線 | なし | なし |
| 所要時間 | 約10〜15分 | 約10〜15分 |
| 得意なこと | プラークの質的評価、血流の動態 | 広範囲の血管形態、脳内の微細な変化 |
【頸動脈MRI(MRA)についてはこちら:頸動脈MRI/MRAとBlack-Blood法で脳梗塞を予防する】
🩺 当院での組み合わせのメリットと総合評価
- エコーで「血管の今の動き」と「危ないプラークの性状」を詳細に確認
- 脳梗塞の直接的な引き金となる不安定プラークを見つけ出します。
- MRIで「どれだけ狭くなっているか」と「脳内の血管」まで広範囲に評価
- 脳全体への血流の影響や、脳内の微小な梗塞の有無まで確認します。
⇒ 両方の検査を組み合わせることで、頸動脈の状態を「点」だけでなく「線」で捉え、脳梗塞リスクの全体像をより深く、正確に把握することが可能になります。
「無症候性脳梗塞」と「脳梗塞の前兆」を見逃さないために
「脳梗塞は突然起きる」というイメージが強いかもしれませんが、実はその前に、「無症状の狭窄」や「不安定プラーク」が隠れているケース、あるいは「脳梗塞の軽い前ぶれ(一過性脳虚血発作:TIA)」が起きているケースが多く存在します。これらのサインを見逃さないことが、脳梗塞の予防には極めて重要です。
特に以下のタイプの方は、自覚症状がなくても注意が必要です。
頸動脈エコーをおすすめしたい方:このような症状・リスクがある方は要注意
- ✅ 健診で血圧・コレステロール・血糖値が高めの方
- 高血圧、脂質異常症、糖尿病は動脈硬化の主な原因です。
- ✅ 喫煙歴のある方
- 喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を進行させます。
- ✅ ご家族に脳梗塞・心筋梗塞の既往がある方
- 遺伝的な要因も無視できません。
- ✅ 最近、ふらつき・もの忘れが気になる方
- 脳血流の低下や、軽微な脳梗塞の可能性も考えられます。
- ✅ 過去に一過性脳虚血発作(TIA)の経験がある方
- 「手足のしびれが数分で消えた」「一時的に片方の目が見えにくくなった」「ろれつが回らなくなったがすぐに治った」などの経験がある方は、脳梗塞の前触れである可能性があります。
- ✅ もちろん、「血管の今の状態を知っておきたい」という健康意識の高い方にも、脳ドックの一環としておすすめです。
当院の頸動脈エコー検査体制と脳神経外科専門医によるサポート
けやき脳神経リハビリクリニックでは、患者様一人ひとりの状態に合わせた、最適な脳血管の総合評価を行っています。
- 頸動脈エコー検査(即時評価): 経験豊富な検査技師が丁寧に検査を行い、リアルタイムで血管の状態を評価します。
- 頸部MRA(広範囲の血管可視化): 頸動脈だけでなく、脳に入る手前の血管全体の形態や狭窄度を評価します。
- 頸動脈MRI(プラーク内部の性質まで分析): プラークのより詳細な内部構造を解析し、その危険度を精密に評価します。
- 🧑⚕️ 検査は専門の検査技師が丁寧に行い、結果は脳神経外科専門医が詳しくご説明いたします。他院での検査結果が気になる方のセカンドオピニオンとしてのご相談も可能です。ご自身の血管の状態を知り、具体的な予防策について専門医と相談することで、将来の不安を解消しましょう。
頸動脈エコーで未来の脳梗塞を防ぎましょう
頸動脈エコーは、脳の血管トラブルを未然に防ぐための「早期警報装置」とも言える、非常に重要な検査です。
当院では、頸動脈エコーと頸動脈MRI(MRA)を組み合わせることで、
- 血管の内側の「変化」
- 危険なプラークの「性質」
- そして脳全体の「血流の流れ」
までを包括的に評価できるのが大きな強みです。これにより、単なる血管の狭窄だけでなく、脳梗塞の真のリスクを見極めることが可能になります。【頸動脈MRI(MRA)についてはこちら:頸動脈MRI/MRAとBlack-Blood法で脳梗塞を予防する】
「自分の血管の状態がどうなっているか、一度チェックしてみたい」「健康診断の結果に不安がある」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。早期発見・早期対策が、あなたの未来の健康を守ります。
頸動脈エコーに関するよくある質問(FAQ)
検査に痛みはありますか?
ありません。ゼリーを塗って、皮膚の上から超音波を当てるだけの検査ですので、痛みや不快感は全くありません。
検査は保険適用されますか?費用はどのくらいですか?
医師の判断により、特定の症状やリスク因子がある場合には保険適用となる場合があります。まずは医師にご相談ください。ご自身の判断で検査を受けたい場合は、自費診療となることもあります。
健診で異常がなかったのに、頸動脈エコーは必要ですか?
はい、非常に有用です。一般的な健康診断では、血圧やコレステロール値といった「血液の状態」はわかりますが、「血管そのものの内側の変化」は直接確認できません。頸動脈エコーは、健診では測定されない動脈硬化の進行度や、脳梗塞のリスクを高めるプラークの有無・性質を直接見ることができるため、健康診断とは異なる視点であなたの血管の健康状態を評価できます。
検査結果はいつ、どのように聞けますか?
頸動脈エコー検査は、通常、検査当日に結果について医師がご説明いたします。必要に応じて、後日改めて詳細な結果説明の機会を設けることも可能です。
検査時間はどのくらいですか?特別な準備は必要ですか?
検査自体は約10〜15分で終了します。特に食事制限や薬の服用制限などの特別な準備は必要ありません。普段通りの服装でお越しいただけます。
検査で異常が見つかった場合、次のステップはどうなりますか?
検査で動脈硬化の進行やプラークが確認された場合、その状態や患者様の全体的な健康状態に応じて、今後の治療方針や生活習慣の改善について詳しくご説明します。必要に応じて、専門の医療機関へのご紹介や、投薬治療の開始など、最適な脳梗塞予防のための具体的なプランをご提案させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。